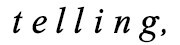メンタル不調に動じない女たち
「ひとり会議」で感情を紐解く
Cさんは、PR会社で働く28歳の女性。昨年11月にチャット形式で「ひとり会議」ができるメモアプリをインストールした。ひとりで複数人の役をチャットで演じ分け、「何が一番悔しいの?」「私のエンジン(頑張る源)になっているものは何?」など自らに問いかけてみている。自分の感情を深く知るために使っていると言う。
アプリを使うきっかけは、職場のカウンセリングルームに行ったことだ。仕事の繁忙と、懸けていた試験の結果が思うようにふるわなかったことが重なり、「何もかも終わった」と放心状態になっていた。「突然涙が出てきたり、電車を乗り過ごしたり、私、やばいかもしれないと思って――」
カウンセラーと話し、「自分の感情を紐解いていくといいかもね」とアドバイスをもらって、特に最近はアプリなどで便利なものもあるらしいという話から、このメモアプリを使うことに。

結婚3年目の夫とは何でも話せる関係で、普段だったら悩みや愚痴も気兼ねなく共有するが、この時は違った。自分の感情が「いっぱいいっぱい」になって自分でも理解できていないままに、彼に説明しようとしても「いっぱいいっぱい」の感情を追体験するだけでつらくなってしまい、うまく言葉にできないことに自分でも苛立ってしまった。
「ひとり会議」アプリの記録を振り返ると、Cさんというひとりのなかに、さまざまな人格の自分がいることに気づいたと言う。強気な自分、弱気な自分、ロジカルな自分……。ぐちゃぐちゃに絡まっていた感情が複数の人格に分かれることで、「本当は自分はどうしたいのか」、一番素直な自分が見えてくる。アプリでは、それぞれの役ごとにアイコンを変えられるから、「人格」の使い分けがしやすいのかもしれない。
ちょっとした気分の落ち込みは、趣味の散歩やサウナに行くことで解消できるCさん。そんなCさんにとって、メンタル不調とは、「前に行くことも、後ろに行くこともできない」状態のようだ。次の歩みをどこに進めたらいいのか分からなくなると“ガクン”と来てしまうが、自分のいろいろな感情を紐解いていくことで、本当はどうしたいのかが分かると落ち着くのかもーー。向上心が強いCさんは、メモアプリで感情を解きほぐすことで、次の打ち手を見つけ、それが自身の心の安定につながることに気づいた。「もしかしたらすごく私らしいやり方なのかも」とCさんは言う。自分にあった方法に出会えたことで、もし不安定になってもこれがあるという安心材料となったのか、最近心の状態は安定している。

次に話を聞いたのは、36歳で0歳の子どもがいるSさん(イベント制作会社勤務)。Sさんは、2020年の初めから「日記アプリ」を使用し、節目のタイミングや感情がモヤモヤとした時に書き込んでいると言う。
大失敗の経験から「予防策」
Sさんが自分の感情と正面から向き合うようになったきっかけは、自身の離婚経験だという。離婚するまでは自由奔放に生きてきた。ある年のクリスマス、ノープランだったことを当時の夫にあたった。Sさんの準備不足でもあるし、実はそれほど記念日のお祝いをやりたいと思ってもいなかったのに、「リコン、リコン!」と冗談で言ってしまい、その言葉が夫のなかで重く響いた。「結婚したし、なんでも許してくれる」という甘えが、結果的に離婚のひとつの理由になったのだとSさんは話す。自分の感情と自ら向き合わず、全部相手にぶつけてしまった失敗があるからこそ、今は「自分の心の芽に向き合い、ちゃんとお水をあげないと枯れてしまうんだ」と思っている。
Sさんが「日記アプリ」に記しているのは、主に自身の感情について。読み返した時に、「こういう感情になっていたんだ」と振り返ることができるから、仕事の「1 on 1」と同じ感覚で自分の感情や内面の成長を見返す「成長ツール」のような存在になっている。Sさんは、昨年再婚し、出産して今は育児に奔走する日々。だが、つい先日も友人たちで集まった時に、夫のいる前で夫を下げた話し方をしてしまい、その反省を日記アプリに記していた。人に話すだけだと忘れてしまうかもしれないけれど、この記録があれば、同じことは繰り返さないだろうと思う。
もともとSさんは、感情の浮き沈みが「結構ある方」だと思っている。そんな感情の行き場がなくなった時は、今でもやっぱり爆発させるしかない時もある。この前のゴールデンウィークも夫が自分の予定で忙しく、子どもと家で留守番が多かったSさんはイライラがつのり、「どっか行きたかった!寂しい!」とストレートに怒った。その時の日記アプリには、「キレすぎた」と反省が記されている。気持ちの「解消」というより、次また同じ失敗や不調に陥らないように「予防」している感覚に近いとのこと。

人生において、一番会話しているのが「自分」――。自分自身の感情や気持ちと向き合うことをおろそかにしてしまうと、人に迷惑をかけたり、家族も仕事もうまくいかなくなったりする。Sさんのメンタル不調との向き合い方は、徹底的に己の感情に向き合い、自らを省みることで次に繋げようとする自省型なのかもしれない。
脳の「癖」と付き合う
最後に話を聞いたのは、未就学児がいるMさん(34歳、IT会社勤務)。先月、心療内科でADHD(注意欠如・多動症)との診断を受け、現在は通院している。
ADHDという言葉は、大学生の頃に知った。サークルの先輩がSNSで「自分はADHD」だと発信しており、常になにか動いているような異常なまでのアクティブさに、自分もどこか近いものを感じていた。詳しく症状を調べてみると、自分で自分がコントロールできなくなることがある一方、頭の中は常にアイディアが溢れていていわば「ポップコーン」のような状態であるなど、ポジティブな面もあると感じた。
しかし、社会人になると、本来はその時に集中しなくていいものに集中してしまう、納期が守れないなど、不都合が出て来た。結婚し子どもが産まれてからは、何かとうっかりな行動が多く現れはじめ、反対方面の電車に飛び乗ってしまったり、手荷物をまるごと出先に置いてきたり、夫と子どもの待ち合わせの時間に間に合わなかったりすることが続いた。夫から見ても、どうにも看過できなくなってきたことから、夫に脳の検査を勧められ、病院に行くことにした。

「ADHDというと、心やメンタルのことだと思われるけど、脳のことだから」――。
心療内科へ行くことに当初は少しハードルを感じていたが、診察を受けると先生の言葉に大きく頷いた。その後は、ADHDの症状が出ても、「あ、私の脳の“癖”が出ているな」と冷静に思えるようになり、自分の「性格のせいかもしれない」などと自分を責めたり自己嫌悪に陥ったりすることが少なくなった。そういう脳の症状なのだと自覚すると、こんなにも楽になるなんてーー。それまでの私は、無駄に落ち込みすぎていたな、と思うこともあるのだそう。メンタルが沈みきる前に、自分の脳の「特性」を知って向き合うことは、Mさんの気持ちを大きく変えた。
心を許した友人には、ADHDだと打ち明けているが、その反応はさまざま。受け入れてくれる人や、「私もそうかも」と興味を示す人もいるが、特に印象的だったのは会社の同僚が「絶対そんなことないって……」と過剰に否定してきたことだ。MさんはADHDを「恥ずかしい」と思っていなくても、一般的な世間の反応はこうなのかも、と思った。
通院後でも、自分で自分のメンタル不調に対処するのは、正直かなり難しい。それでも、もともと病院に行くことを勧めてくれた夫は「わかることが大事」「わかれば対処できるから」と冷静な反応で、「できないことは先にできないと言ってほしい」と言われた。暇でいることが苦手で予定をつい詰め込みすぎてしまうMさんのことも、「僕は違うけどね」と言いつつ夫は理解してくれる。「お互いが気持ちよく過ごせる状態を知ることで、歩み寄ることができた気がするんですよね」と、Mさんは言った。

7割がメンタルコントロールに関心
博報堂キャリジョ研プラスは今年5月、未婚・既婚問わず20-40代の女性100名を対象に「メンタル不調の自覚に関する調査」を実施した。「メンタルを整える」ことに関心がある女性は7割以上と高い結果になった一方で、「関心がある」と答えた女性たちのなかで「メンタル不調について対策をしている」と答えたのは5割弱だった。自身の内面を「整える」ことについては多くの女性たちが興味を持っているけれども、その対策までたどり着いているのはまだ一部のようだ。
【グラフ1】

また、対策している人のなかで最も多かった方法は「趣味の時間でストレスを発散する」で21.3%。次いで「睡眠時間を十分にとる」「軽い運動を行う」「バランスのいい食事」などが挙がった。本インタビューで見られた「外部の病院に相談する」は7.4%、「自分だけにとどめた場所で感情を記録する」は6.4%という結果になった。その他では「薬を飲む」など治療に関するものもあった。
【グラフ2】

メンタル対策をするようになった「きっかけ」については、産後の不安定さ、コロナ禍などに加え、うつ病やパニック障害と診断された人もいた。自由記述欄には、「40歳近くなり、自分の機嫌は自分で取りたいから」と年齢をきっかけに向き合おうとする声もあった。
今回の取材を通して、自分の感情の起伏と真っ直ぐに向き合い、その感情の原因を紐解く大切さを感じた。彼女たちが自分なりの対処法を見つけようと努める姿が印象的だった。
この投稿をInstagramで見る