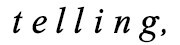子どもファーストで生きない女たち まずは自分の意思が優先
生後2か月半で産休から復職
メディア業界で働くSさん(36)。昨年1月末に出産し、4月には保育園に入れて仕事に復帰した。首も座っていない生後2か月半の子どもを預けて復職したことに、職場の人は驚いたという。もっと休まなくて大丈夫か心配してくれる声もあったが、Sさんとしては、仕事にブランクがほぼ何もないし、その後の仕事に問題がないことを伝えると、子どもがいる、いないに関係なく、分け隔てなく仕事が割り振られた。
「子どもがいると出張に行かせることなどに抵抗がありそうですけど、私の上長は他の人と同じように出張させてくれました。それが自分にはありがたかったです」

希望の保育園に空きがでて、たまたま入れてしまったというのが実情だけれど、周りには会社経営者や医者なども多く、彼女たちは産後数か月で復帰していたので、それも影響したかと思う。Sさんは出産したことで、キャリアに分断が起きることが嫌だった。「将来自分の子どもが、自分のせいで母親がキャリアをあきらめないといけなかったと思ってしまったら、それが一番嫌です。それに私にとって仕事をしている時間は一人の人間としていられる時間となり、もはや癒しの時間になっています。仕事にすぐに戻ることで、子育てでブレブレになるメンタルを保てました」
また、保育園に入れたことで、ミルクや離乳食の用意の仕方など、先生たちに助けてもらったり教えてもらったりすることも多く、学びがたくさんある。「そこで娘のことは全部賄えていて、自分だけが気負ってやらなくていいというのが精神的に非常に有難かったです。自分ファーストで動くことで、結果的に自分と娘の良好な関係と、娘の成長に繋がっていると思います」
飲み会にも積極的に
Sさんは毎日ずっと子どもと二人で家にいると、どうしてもストレスが溜まってしまうので友達とも積極的に出かけたいと思っていることを周囲にも話している。ベビーシッターや家族に娘を預けて月に数回は夜の飲み会などにも参加している。シッターさんはプロなので、上手に遊んでくれて、子どもも楽しそうだ。そしてSさんも夜の会を楽しむことで、そういう時間でないと話せないことや、食べられないものを楽しんでいる。もちろん、時間の制限があるので、パッと行ってパッと帰ってこなくてはいけないが、その分気持ちを集中して楽しんでいる。

生き生きとした表情でSさんは続ける。「会社の先輩たちとの飲み会に娘を連れて行ったこともあります。娘は保育園では最年少というのもあり、色々な年齢の子どもや大人にかまってもらうことに慣れているので、他人に物おじせず色々な人に自ら関わろうとします。なので先輩たちに相手していただくのも嬉しそうでしたし、いい経験になっているだろうと感じます。色々な人と活発に交流することが娘にとって良い影響になればと思っています。」
子どもを大人と平等に扱う
金融業界に勤めるOさん(48)。10歳になる息子がいる。サッカークラブに入っており、チームの子の親たちと会うことがある。また小学校でも保護者の集まりはある。そういったとき、Oさんは子どもたちを子ども扱いしない。例えばアイスを買ってきて、みんなでその中から好きなものを選んでいくとき、周りの親たちは子どもに先に選ばせようとする。
「でも私は、子どもの友達から『子どもが優先でしょ?』とか言われても『なんで?私も○○味がいいよ。全員でじゃんけんしよう』など言っています」。子どもたちは甘やかされることに慣れている子も多いと感じる。他の家の子どもから「ほかの大人は子どもを優先するよ」と言われることもある。でも「え?なんで優先なの?なんで??」と疑問をしっかり口に出しているそうだ。誰々の親がそう言っていた、と子どもに返されると、「じゃあその人にお話ししてみるね」と対応している。そして実際に自分の考えをその親に説明しているという。
「子どもだとしてもちゃんと説明が必要な場合は、子ども用の言葉は使わず『私は他とは違うよ。いろんな考えの人がいるよ』と答えるようにしています。周りには私のことを怖がっている親子もいると思いますが、優しい人が多いなか、一人くらいこういう人がいてもいいと思っています。半分は教育として子どもを一人の人間として扱うべきという気持ち、残り半分は子どもの甘やかされぶりにイラっとして、言葉にしています(笑)」

もちろん、時には子どもを優先したほうが自分が楽なこともあるので、いつもそうできているわけではない。お手伝いでもまだ包丁を持たせたら危ないし、電車で席がひとつ空いていたら子どもに座らせた方が大人しくするので楽なこともある。
「でも例えば電車で席を息子に譲っても、『座らせてあげるけど、お母さんは48歳、一日お仕事して大変だったんだからね』というアピールをします。譲るけど、自分の主張もしておく、というのを大事にしています。子どもはすぐにイヤだとか、疲れたとか言うけれど、親も同じようにイヤだとか不満を感じているということを覚えさせるため、『あーいやだ、お母さんも面倒くさい、無理』と対抗します(笑)」
家事も任せてみる
Oさんは以前、ある芸能人が、自分の母親の子育ての仕方を語っている記事を読んだことがある。その人が小さいころ、母親にりんごを食べたいと言うと、母は切ってくれるわけではなく、「リンゴとナイフあるよ」と言っただけだったそう。Oさんは子どもを大人と同じように見る子育てに感銘を受けた。
実際、Oさんもまた、似たような母親の元で育った。Oさんは3兄妹だったので、かなり育児は大変だったというのもあるが、自立した子どもに育てたいという意図があり、Oさんの家では、子どもも家事を担当することは当たり前だった。
料理で火やナイフを使うなどは小学生の頃から始めていたし、食器を洗うのは兄とOさんのどちらかが担当していた。電車でおつかいにもいっていたという。

「多分、お皿を割るなど逆に手間になっていた部分もあったとは思うけれど、私はこういう経験を小さいうちからできて本当によかったと思います。逆に、小さいうちから自分で色々とできないと、ぼんやり育ってしまうように思います。うちの子どもは遅くに産んだこともあり、正直可愛くて仕方なくて甘やかしそうになります。時には大人と平等に扱えないことも多々あるけど、意識だけはちゃんと持っていたいと思っています」
習い事はさせない
Uさん(38)はメーカー勤務。現在1歳と、7歳の子どもがいる。今の時代、子どもが小学生になる前後になると、習い事をさせる親が多い。しかしUさんはあえて子どもに習い事をさせていない。時間的も金銭的にも親の負担になるのでイヤなのだそう。
「周りには0歳からリズム遊びとか、英語を習わせる親も多い。5歳になると3つやっている子も。それを聞いても何もやらせませんでした。それより自分がリラックスできる時間をとりたかったんです」
子どものことを考えてのことでもある。Uさんは親が思い立って始めた習い事は、子どもの自由を奪っている感じがするそう。「あくまで個人の考えですが、多くのスキルをかじることに、あまり意味はないのでは?と思っています。ピアノやそろばん、水泳と、あれこれしてもそれほど身につかないし、かえって子どもの自由や時間を奪っている気がします。なにか一つを頑張ることで、やり遂げることや我慢することを覚えるとか、ソフトスキルを身につけるのはいいと思いますが」

少なくとも一般的な習い事は、指示されたことをその通り行って練習する、“受け身”の姿勢が多いと感じる。「指示待ちの人間になってほしくはない」との思いもあるそうだ。それよりは子ども自身がやりたいと思ったことを、自分で考えた範囲でやってみる。そういう時間を増やしたいと思っている。
「習い事をさせてないことや、今1歳になった子どもを保育園に入れていることなどは周りにも話していますが、とやかく言われることはないです。時々、ものすごく時間や労力をかけられている子どもを実際に目の当たりにすると、何も言われなくても勝手に焦ることもないとは言えませんが、それでも子ども自身がつらくならなければ自分のやり方は変えたくないです」
まずは仕事を頑張りたい
子どもに色々と時間を割くと、仕事の時間が減る。Uさんは仕事の時間も大好きなのだ。「私の母は専業主婦でしたが、全然楽しくなさそうでした。育児も家事も好きじゃないのに、なぜ専業主婦になったか謎なくらい。そういう姿もみて、自分は専業主婦にはなりたくないな、仕事を頑張りたいなと思っていたのかもしれません」
子どもの頃、芸能人やテレビ関連の仕事をしている女性たちをみて、とても楽しそうにみえた。「昔よく読んでいたファッション雑誌にジュエリー特集があったんですが、ある女性俳優さんが仕事を頑張った時に自分でジュエリーを買うと言っていました。そういう風に仕事を頑張りつつ、ご褒美を自分で用意するような人生に憧れがありました。そして、今実際にそういう風に仕事も頑張って充実させて、充足感を感じているからこそ、子どもにも優しく対応できるのだと思います」

自分のこだわりを優先する
メーカー勤務のIさん(46)は、美大に通っていたこともあり、人に同調しない個性や、美しいものへのこだわりが強い。13歳、8歳、5歳の子どもがいるが、服など身の回りのものは、Iさんが提案したものを着せている。保育園ではアニメが流行し、そこに出てくるキャラクターの服を多くの子どもたちが着ている。フリフリした服も人気だ。
しかしIさんは、自分の子どもたちにはそれに同調してほしくなかった。Iさんにとって本当に美しいと思ったものを着てほしいという気持ちもあり、周りが着ているからといってキャラクターの服やフリフリした服は着せなかった。
「子どもからそういう流行の服を買ってほしいと言われることはあるけれど、私は自分が美しいと思えないものを身の回りに置きたくないと思っています。自分の子どもにも審美眼を育んでほしいです。また、いつか考えが周りと合わなくなって孤立したとしても、折れないでほしいとも思っています。今のうちから人とは違うことは悪いことではないということを伝えたいんです」
子どもが低年齢ほど優先する傾向
【グラフ】(単一回答)

博報堂キャリジョ研プラスは2025年1月、20-49才の女性100人を対象に「子どもと、自身のライフプラン・生活の関係性に関する調査」を行った。上記グラフの調査対象者は回答者全体から子どもの年代を記載しなかった人、23歳以上の子どもを持つ人を除く92人。
未就学児の親は母集団47人、小中学生の親の母集団は34人、高校生大学生の親の母集団は7人。高大学生の親の結果は、母集団が小さいため参考値とする。
グラフを見ると、「キャリア」、「居住地」(住む場所・環境)に関して何か意思決定を下さないといけない場合は、「子どもの意思を優先する」「どちらかと言うと子どもの意思を優先する」と答えた人が、未就学児の親ではそれぞれ、57.4%、61.7%、小中学生の親ではそれぞれ38.2%、50.0%と「自分の意思を優先する」「どちらかと言えば自分の意思を優先する」人よりも多い。一方で「日常生活」(食事や娯楽など)の決定に関しては、「自分の意思を優先する」「どちらかと言えば自分の意思を優先する」と答えた人が未就学児の親では計38.2%、小中学生の親では計32.3%と、「子供の意思を優先する」「どちらかと言えば子供の意思を優先する」人よりも多い。概ね、子どもの年齢が低いほど、親は子どもの意思を優先しがちな傾向があるようだ。また、日常の決断より、キャリアや居住地の決定という大きい決断の時の方が、子供の意思を優先することがありそうだ。
調査では、フリーアンサーで、自分の意思を優先する具体的なエピソードを尋ねてみた。
・自分のストレスを子どもにぶつけないように、ある程度自分の意思も通すことが大事だなと思うこともある (女性、26歳、4歳の子)
・仕事の残業・休日労働:お金がなければ子どもにとっても欲しいものは買えないので、働けるときにしっかり働きます (女性、47歳、14歳の子)
・住みやすい郊外ではなく、通勤に便利な都市部に住んでいる (女性、29歳、1歳の子)
・養護者の大人の環境を整えることで良い影響を子どもに与えたい(女性、41歳、11歳と8歳の子)
今回のインタビューやアンケートから、自分の意思を尊重しつつ、結果として子どもの自立を促したりするよう心がけている母親も少なくないことが分かる。あえて、子どもより自分の意思を優先していることを周囲に伝えている人もおり、女性の社会進出が進む中で、子育てに関して親の意思を優先することを声に出しやすい環境になっているのではないかと感じた。
この投稿をInstagramで見る