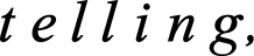体験談を読む
「『特別』だけど特別じゃないんだ」アメリカの特別養子縁組を体験したこどもたち
鮫島浩二さん、鮫島かをるさん、あさひさん(仮名)

「こどもたちに広い世界を見せてあげたい」。そんな思いで、大人たちが特別養子縁組のこどもたちをアメリカのホームステイへと送り出しました。アメリカは約50人に1人が養子といいます。アメリカでの経験でこどもたちは何を感じ、何を得たのでしょうか。ホームステイを体験したこどもと、企画・運営した「さめじまボンディングクリニック」の鮫島浩二院長・かをる事務長のご夫妻にお話を聞きました。
多くの人に支えられ、旅立ちへ

――「さめじまボンディングクリニック」は産婦人科クリニックの中に、こどもを望む夫婦のための「望児外来」も設置しています。2018年には特別養子縁組のあっせん事業者としても埼玉県から認可を受けており、これまで約150組の親子の縁組を支援してきました。なぜ、特別養子縁組のこどもたちのホームステイを思い立ったのでしょうか。
かをるさん:2023年に浩二院長がひざの手術を受けたのですが、術後の経過が悪く、生死の境をさまようような時期がありました。幸い快復したのですが、入院期間に人生について考えるにあたり、「特別養子縁組の当事者のこどもたちをアメリカに連れて行きたい、広い世界を見せてあげたい」と、突然ひらめいたようなんです。浩二院長自身、大学生のころにアメリカにホームステイをして人生観が変わるような経験をしたので、それをこどもたちにも経験してほしいという思いがあったそうです。
浩二さん:私たちが縁組をサポートしたこどもたちも大きくなって思春期に入ってきています。広い世界を見て、自分について考えてほしいという思いがありました。アメリカはたくさんの特別養子縁組家庭がある「養子大国」です。そんなアメリカのこどもたちと交わって、「自分は決してマイナーな存在じゃないんだ」ということに気づいてほしいと考えました。
かをるさん:これまで多くの特別養子縁組を支援してきて、日本では不妊治療などの結果こどもを授からなかったご夫婦が特別養子縁組を検討するケースが多いと感じています。それ自体全く悪いことではないと思いますし、私たちもそういったご夫婦を支えたいと考えています。一方アメリカは「社会的養護のこどものため」という意識が広く浸透しており、実子がいようといまいと、多くの人が特別養子縁組をしています。こどもたちには「こういう世界もあるんだよ」ということを知ってもらいたかったのです。
――ホームステイのための費用をクラウドファンディングで募ったところ、目標額を超える寄付が集まったそうですね。
浩二:ありがたいことに目標金額を大きく上回る寄付をいただき、費用をまかなうことができました。養親さんやそのご家族など、いろいろな方たちからご支援をいただきました。
とても印象的だったのは、ご自身がこどもを特別養子縁組に託した、生みの親の立場にある方からのご寄付があったことです。ホームステイに行くこどもたちとは直接の関係はないのかもしれないけれど、特別養子縁組のこどもたちにこのようなチャンスをつくってほしいという思いがあったようで、とても感動しました。
こどもたちも、会ったこともない大勢の方たちに応援してもらってアメリカ留学を経験させてもらったということは、ずっと心に残ると思います。
「私、養子なんだ」 伝えても誰も驚かなかった

――実際にアメリカに滞在した当事者のお子さんにもお話を聞きたいと思います。あさひさん(仮名)は中学1年の夏休み、2024年7月から8月にかけてアメリカにホームステイしました。どんな思いで参加したのですか。
あさひさん:私はこれまでお父さんお母さんと離れるのが嫌で、修学旅行のときも宿泊学習のときも、行く前はずっと「嫌だな。行きたくないな」と思うタイプでした。行ってみたら楽しいのですが。中学生になったことですし、一回殻を破って親元を離れ、思い切って行ってみよう! という気持ちで参加しました。海外は初めてです。それから、アメリカの特別養子縁組家庭がどんな感じなのか、養子として知ってみたい、見てみたい気持ちもありました。
私がホームステイさせていただいたおうちはこどもがいる人同士が再婚した「ステップファミリー」でした。言葉の壁はあったけれど、簡単な英語や身ぶり手ぶり、スマホの翻訳アプリなどを使ってコミュニケーションを取ることができました。家族も、私の言いたいことをくみ取ってくれて、対応してくれました。
他の家族との集まりや、教会での交流会にも行きました。そのとき印象的だったのは、私が特別養子縁組の養子だということを相手に言っても「そうなんだー」くらいの反応だったことです。特別養子縁組の養子は、日本ではまだまだ珍しい存在だと思っていました。小さい頃友だちに「私はお母さんから産まれていなくて、別の人から生まれたんだよ」と話したら「そんなわけないでしょ」と言われたことがあって。小学校1年生で幼かったというのもあるのでしょうが、「お母さんから生まれていなくても何も違いはないのにな」と、寂しい気持ちもありました。
アメリカでの経験を経て、「『特別』養子縁組は、特別じゃないんだな」と感じることができました。

かをるさん:他のホームステイ先に行った子も、最後まで自分のステイ先のこどもたちが養子だと知らなかった子もいました。「全員実子だと思っていた」と。養子も実子もわからないくらいに家族になじんでいるということで、そのエピソードがアメリカの特別養子縁組のあり方を象徴しているように思いますね。
アメリカに行ったこどもたち同士も仲良くなり、結束が強まりました。特別養子縁組のこどもは日本では数も多くなく、孤独を感じがちです。同じ立場のこども同士が一緒に旅したことは、自分は孤独じゃないんだということを認識してもらえたんじゃないかと思います。帰国後、成田空港で養親さんたちはいまかいまかと待ち構えていましたが、こどもたちは解散するのが名残惜しそうなくらいでした。
浩二さん:あさひちゃんのステイ先のお父さんお母さんも、あさひちゃんをとても可愛がってくださった。国境や言葉を超えて、愛情深い人に守ってもらう経験をできたことは、一生の宝になるのではないでしょうか。
私も引率でこどもたちと一緒に渡米しました。夜、アメリカの空港に着いたときはみんな少し緊張していましたが、それぞれのご家庭に迎え入れられた翌朝にはもう笑顔いっぱいで、言葉の壁なんてどこかに吹っ飛ばしてしまっていました。ホームステイ先も基本的には特別養子縁組のご家庭なので、異国の地の特別養子縁組の養子たちと触れあうことができました。
あさひさん:私もすごく温かいおうちに迎え入れてもらいました。とても「ほんわか」したご家庭だったので、私の気持ちも「ほんわか」しました。滞在期間の1週間があっという間でした。
多くの人に特別養子縁組を知ってほしい

――アメリカでの経験を踏まえ、日本でこれから特別養子縁組について知ろう、特別養子縁組のために動きだそうとしている人たちへのメッセージをお願いします。
浩二さん:特別養子縁組制度が日本でできてから40年近くが経ちますが、いまも約4万人のこどもが施設で暮らしています。今は制度自体がしっかり整い、これからは養親さんの支援に力を入れていくべきだと思っています。私たちは養親さんたちを支え続けていきますし、国と一緒にこどもたちの未来をつくっていきたいです。アメリカでの経験も経て、こどもたちに国際的な感覚を身につけることをサポートしたい思いもできました。ホームステイの試みは、これからも続けていきたいです。
血のつながりがなくてもこどもを育てていきたい、そう感じているご夫婦にぜひこどもを託せればと考えて私たちは活動を続けていきますし、こどもたちのことも様々なかたちで支えていきます。

あさひさん:特別養子縁組についてもっとたくさんの人たちに知ってもらえれば、養子が「生きづらいな」と感じることも減っていくのではないかと思います。特別養子縁組について、日本で知らない人がいないくらいになってほしい。もし、特別養子縁組をしようかどうしようか迷っている人がいるのなら、絶対してほしいなと私は思っています。施設にいて、家庭がどのようなものか知らない子も多いと思います。そのような子に家庭で暮らして、親の愛を知ってほしいです。居場所がない子に居場所をあげてほしいです。
かをるさん:あさひちゃんが言うように、特別養子縁組って「特別」なことではないです。夫婦ふたりで人生を送るのもすてきなことだけれども、「血のつながりはなくとも、こどもを育てる」という経験をふたりでするのも、素晴らしいことです。苦労は伴うかもしれないけれど、喜びはその何倍もあります。こどもと一緒に成長していけるのはかけがえのないことです。あさひちゃんのご家庭も笑いが絶えない、自然体で明るい家族です。そんな素晴らしいご家族を見ていると、迷っている方には一歩を踏み出してほしいなと思います。


- すべて
- 養親当事者の想い
- こどもの想い
- 専門家の解説
- 周囲の想い
- 不妊治療