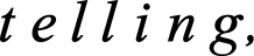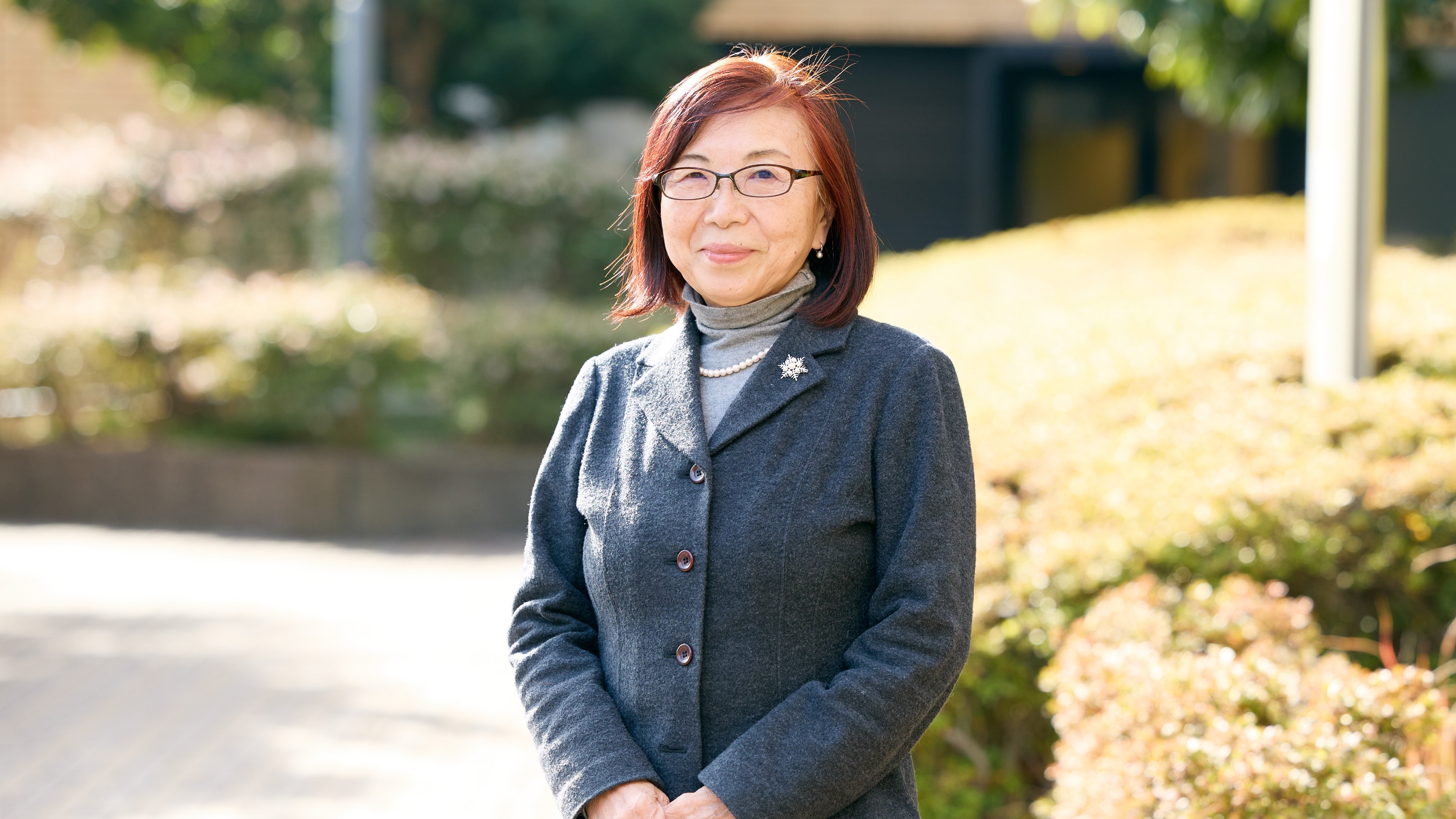体験談を読む
こどもと養親との双方向から
こどもの生い立ちを整理する
「ライフストーリーワーク」
徳永祥子さん

「私はどんなところで生まれたの?」「私を産んだお母さんはどんな人?」――こどもにとって、自分のルーツを知りたいと思うのは自然な気持ちであり、自らの生い立ちを知ることは自己形成において不可欠です。一方で養親にとっては、どう伝えたらいいか、悩ましく緊張する事柄でもあります。イギリスで生まれた「ライフストーリーワーク」は、こどもと養親が一緒になって生い立ちを解き明かしていく「共同作業」です。日本でのライフストーリーワーク研究第一人者である徳永祥子さんは、「血のつながらない親子だからこその、愛情を伝えるチャンス!」と言います。
※Amazonギフトが当たる!アンケート実施中※
本サイトのコンテンツを閲覧いただいた上でアンケートにご協力ください。
ご回答いただいた方の中から、50名にAmazonギフト券500円分を抽選でプレゼントいたします。
アンケートには、本記事の最後にあるリンクからお進みいただけます。
こどもの「ストーリー」をしっかり伝えていく

――ライフストーリーワークのひとつに、「こどもに生い立ちを伝える」というものがあります。そもそもなぜ、特別養子縁組のこどもに生い立ちを伝える必要があるのでしょうか。
国連の「子どもの権利条約」では、「こどもの『知る権利』を保障する」と定めており、日本の児童福祉法も、その精神にのっとるとしています。出自を含むこどもの知る権利は、私たち大人が守るべき義務でもあります。
ライフストーリーワークは、こどもが自分を責めたり、「生みの親と住めなくなったのは自分が悪い子だったからだ」などと考えたりして自己肯定感を下げることがないように、という趣旨で生まれました。
現代はさまざまな情報を手に入れることができる、情報化社会です。養親が言わなかったとしても、最近はこどももインターネットで様々な検索ができるため、親の名前を検索すると思わぬ情報を目にする可能性があります。こどもが養親に隠れて生みの親に会いに行き、期待していたような対応を得られず、結果こどもの心が傷つくということも、起こるかもしれません。
「いつこどもが特別養子縁組であることに気づくのか」とヒヤヒヤしながら子育てするのではなく、こどもが望まれて養親のもとに来たこと、生みのお母さん・お父さんはあなたが悪い子だから育てなかったのではなく、事情があって育てられなかったから私たちに託したんだよ、ということをしっかり伝えることで、こどもが「私は悪い子・いらない子」などと思わないようにすることが大切です。
私が多くの特別養子縁組のこどもたちの話を聞いて驚くのは、「養親からは教えられていないけれど、血のつながりがないことは何となくわかっていた」と言うこどもが多いことです。不思議なもので、なんとなくわかるようです。他には血液型などを知ってわかってしまうこともあります。
そうすると、こどもにとってそれまで実の親だと思っていた養親が、実の親ではないと気づいた時点で別の存在のように感じられてしまうこともあります。「血のつながった親子」だと信じて築いてきた信頼関係を、あるときから突然「養親との信頼関係」として紡ぎ直さなければならなくなるというのは、こどもにとっては大きな負担だと当事者の若者から聞き、私自身改めてライフストーリーワークの意義を再確認しました。
養親が生い立ちを伝えなかったのは、決してうそをついていたわけではありません。ですが「言わなかった」ということを「うそをつかれていた」とこどもが受け止めることで、これまでの親子関係にダメージを与えるリスクがあります。
だからこそ本当のことを伝え、どれだけこどもを待ち望んでいたのかと伝えることが大切なのです。
こどもの興味関心に寄り添い、ときには一緒に調べる

――こどもに生い立ちを伝えるという方法には、生い立ちについてこどもに告げる「真実告知」、幼いころから生い立ちを隠さず話していく「テリング(tell+ing)」というものもありますが、それらとライフストーリーワークの違いは何でしょうか。
真実告知もテリングも、こどもに生い立ちを伝えるという点ではライフストーリーワークと同じです。ライフストーリーワークが他の2つと違うのは、「I tell you(私があなたに話すね)」ではなく、こどもとの双方向性がより強いということです。
もちろん、話のスタートを切るのは養親です。特に幼いころは養親から「初めてうちに来てくれたときはこうだったね」とか、「○○ちゃんに会えてママとパパは本当にうれしかったよ」などと言い聞かせます。そのうえで、こどもが聞いてきてくれること、興味を持ったことに合わせて話をしていきます。
ときに親が伝えようとしていることと、こどもが知りたいことがずれることがありますが、養親たちには「こどもの興味関心に寄り添ってお話ししてください」とお伝えしています。
・私は愛されているのか
・ここに居場所があるのか
・この世に存在していいのか
そんなこどもの気持ちにまずは寄り添い、そのうえでこどもが「生んでくれたママってどんな人?」と聞いてきたら「どんな人だろう?ママもパパも知りたいな」と、ときには一緒に調べてみる。それがライフストーリーワークです。実際にこどもと一緒に役所や施設を訪ね、生みの親のことを調べる親子もいます。どんな人かわからなかったとしても、こどもの問いに答えようとすることが大事なのです。
決める権利があるのは、こども自身

――実際にライフストーリーワークをするときに大切にしてほしいことはありますか?
「うちに来てくれてありがとう」「大好きだよ」という気持ちは、小さいころから何度も言い聞かせてあげてください。夫婦でアルバムを見ながら、小さい頃のこどもの様子についてあれこれ話すのをこどもが横で見ているのも、ライフストーリーワークの一つです。
親子になった日を「特別養子縁組記念日」にして、お誕生日のように毎年お祝いするのもいいですね。短い時間でいいので「きょうは○○ちゃんが家に来て、そのあと裁判所というところで、『○○ちゃんはママとパパと親子になってもいいよ』って言ってもらった日なんだよ」なんてお話しをしてもいいですね。
発祥地のイギリスで行われている、トラウマからの回復を目指す「セラピューティックライフストーリーワーク」では、ライフストーリーワーカーがこどもに大きな模造紙の上に寝転がってもらって人型を取り、好きなことや得意な教科、どんな気持ちかなど「いま」のことを書き込んでいきます。そしてさかのぼって、生みのお母さんには当時はあなたを育てる準備ができていなかったからあなたを施設に預けたのよ、とか、生みのお母さんはそのときは薬物の影響があったね、など「過去」をしっかり説明していきます。
そして「将来」あなたはどうしたい? と尋ねます。生みのお母さんお父さんに会いたいという話だけでなく、宇宙飛行士になりたい、学校の先生になりたいなどの希望を聞いていきます。
「いま」「過去」「将来」、どこから始めても構いません。

――生い立ちが複雑だったり生みの親に複雑な事情があったりする場合などは、何歳ごろに伝えればいいのでしょうか。
養親としてはこどもが理解できるようになってからと考えるでしょうが、こどもの発達はさまざまです。中には発達障害や、知的障害のあるこどももいます。「発達が進んでから伝えよう」と待っていて、機を逸してしまう場合があります。幼いころから伝え続けていて、あるときこどものタイミングで言葉を理解できるようになりますから、いついつまでは待とう、とは考えなくていいと思います。
大切なのは伝え方です。例えば幼い頃から「大好きだよ」と日々伝える「好き好き大好き貯金」をためてから、養親が「お口の練習」をして、生い立ちを聞かせましょう。
「お口の練習」は、養親がこどもにストーリーをきちんと話せるように練習することです。虐待や遺棄など、過酷な状況から保護されて縁組につながったこどももいますよね。大事な我が子がそんな目に遭っていたということを考えるだけで涙が止まらなくなる養親は、少なくありません。
もちろん、泣いてもいいのです。泣きすぎて話ができないとういうことにならないよう練習しておいて、泣いてしまっても「大事な○○ちゃんが昔つらい思いをしたんじゃないかと思うとママもパパも泣いちゃうの」など、こどもにちゃんと説明ができるようにしておけば大丈夫です。
生まれた状況や生みの親の事情が複雑な場合、ネガティブな情報かもしれないからこどもに伝えづらいと考えるのは当然です。ただ、誰がそれをネガティブだと決めるのでしょうか。ネガティブかどうか、決める権利があるのはこどもだけです。
たとえば、こどもに血のつながったきょうだいがいて、上のきょうだいだけ生みの親のもとで暮らしているとします。養親は「こどもが『自分だけ生みの親に捨てられたんだ』と考えたらどうしよう」と思うかもしれませんが、果たしてこどもがそう感じるかはわかりません。「わたしはママとパパがいる、いまのおうちでよかった」と思うかもしれません。
特別養子縁組の親子だからこそできる愛情表現

――もしもこどもが「聞きたくない」「知りたくない」とライフストーリーワークを拒否した場合はどうすればいいのでしょうか。
もちろんそこはこどものペースに合わせます。「そうか、そうなんだね」とこどもの気持ちを受け止めて、やめます。ただ、できることが何もないかというとそんなことはありません。
例えば夜リラックスしているときに夫婦でアルバムを見ながら「○○ちゃん、初めてうちに来たときは水色の服を着ていたね。生んでくれた●●ママが着せてくれたんだよね」なんて会話してもいいと思います。「新しくアルバム作るから、○○ちゃんはシールを貼ってくれる?」なんて頼むと、意外と乗ってきてくれることもあるかもしれません。
嫌がっているのなら、無理やり言い聞かせる必要はありません。「そういう時期なのね」と受け止めてください。「もし知りたくなったら、ママとパパはいつでも準備ができているよ」ということを態度で示してあげればいいのです。
――ライフストーリーワークをするにあたり、生い立ちを知るためにどのようなところにサポートをお願いできるでしょうか。
まずひとつめは児童相談所です。縁組成立後も、必要に応じてサポートをしてくれます。開示請求をかけることで情報を得ることもできます。また、養子縁組民間あっせん事業者のなかにも、ルーツ探しのサポートやライフストーリーワークの研修会をしてくれる団体もありますし、自治体が委託した機関が、研修や個別相談会を開いている場合もあります。
――養親や、養親候補の方たちへのメッセージをお願いします。
ライフストーリーワークは、たっぷりの愛情をこどもに伝えるチャンスです。血のつながった親子よりも、愛を伝える機会が沢山あるとも捉えられるのではないでしょうか。
「特別養子縁組だからこそ、この子に出会えたんだ」、そんな自信を持って、ライフストーリーワークに取り組んでみてください。
本サイトのコンテンツを閲覧いただいた上でアンケートにご協力ください。
ご回答いただいた方の中から、50名にAmazonギフト券500円分を抽選でプレゼントいたします。
※アンケートはこちら※

- すべて
- 養親当事者の想い
- こどもの想い
- 専門家の解説
- 周囲の想い
- 不妊治療