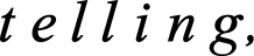体験談を読む
育てることもこどもを託すことも愛
選べる道があることを伝えたい
映画監督、小説家
ふくだももこさん

映画「父の結婚」「おいしい家族」など、多様な家族のあり方、生き方を描いている映画監督のふくだももこさん。特別養子縁組制度の当事者としての発信も続けています。養子として育ったから感じる、家族とは、母とは、こどもとは。2020年に自身も母となり感じた変化についても話を聞きました。
うちはこういう家族。揺るがない気持ちに育てられた
生後4カ月で、乳児院から特別養子縁組で両親に迎えられた、ふくだももこさん。「母が笑顔でいることが父の幸せ」という仲のいい両親のもと、同じく養子の兄と4人家族で育った。
「養子を迎えると決めたのは、母が『不妊治療を長く続けるよりも、養子を迎えたい』と父に相談したら、二つ返事で『いいと思う!』と言われたからだそうです。なぜ父はそう返したのだろう? と母に尋ねたら、『お父さんは、お母さんが幸せであることが一番の人やから』と笑っていました。2人はいまでもすごく仲良しです」
両親は、ふくださんが物心つく前から養子であると「真実告知」をしてきたという。ただ、自分が養子だと理解したのは小学校1年生くらいだったと振り返る。
「いまの家族と血はつながっていなくて、産んだお母さんは違う人――。そう聞いてきた話を、言葉として理解できたのがその頃でした。次の日には、『うちの家族、みんな血ぃつながってへんねんて!』と学校で言いふらしたそうです。同級生の男の子に『じゃあ、ももちゃんって、捨て子なん?』と聞かれて『捨て子ちゃうわ! もらわれ子や!』と返したらしいです。
母は、学校から帰ってあっけらかんと話す娘に、『なんて強い子なんや』と思ったそうです。大阪では、芸人さんが貧乏や人と違う生い立ちを笑いのネタにするのが当たり前だった。だから、自分の一風変わった境遇を『みんなとちがう…なんかおもろいやん!』と、そんな感覚だったんだと思います」

2020年にふくださんも母となり、近くに住む両親と、こども時代の話をする機会が増えているという。「金銭的にも時間的にも、かかるエネルギー量でも、こどもを育てるってすごいこと!」と、両親への感謝はますます大きくなっている。
「赤ちゃんて、こんなに無条件に可愛いんやなあとびっくりしています。血のつながりを感じるのは、母から『寝顔がまったく一緒』と言われるときくらいです。私も母と歩いていると、近所のおばちゃんに『ほんま、お母さんに似てきたわ〜!』と言われたことがあって、人っていいかげんやなあと笑いました。
改めて、私が養子であることをポジティブに受け入れられたのは、『うちはこういう家族でやっていく』という揺るがない気持ちが両親の中にあって、それを自分の中にも育ててくれたからだと思うんです。負い目や不幸を感じることは、一度もありませんでした」

血のつながりがないからこその、自由さもある
映画が大好きな父の影響を受け、中学2年生の頃には「私は映画監督になる」と漠然とした思いを持っていた。
「中学生って多感な時期で大変ですよね。周りのごちゃごちゃとした人間関係が煩わしくて、窓の外を見ながら、どこかに行きたいなぁと思っていた。それが私の中で、暗闇でじっと一つの物語に集中して、いろんなことを考えられる映画のスクリーンのようでした」
映画の専門学校に行きたいという娘を、父は全力で応援し、母はいまも、全作品のポスターを自宅に飾っているという。
ふくださんが描く作品には、現行のルールや価値観に縛られずに生きる人々が登場する。自身が血のつながらない家族で育った「マイノリティー」であるからこそ、作れる物語がある。その強みを前面に出したかったという。
「10代の頃から、世の中のいろんな“あるべき”形やルール、男女の区別やそれに縛られることも、全部めんどくさい! と思っていました。19年に公開した映画『おいしい家族』には、『父さん、母さんになろうと思う』と娘に宣言して男性パートナーと暮らす父が登場しますが、周りの人たちは、それに対して何も言わずに当たり前に生活している。早くこういう世界にならないかな、と思って作品をつくりました。
世の中には、血のつながりを描いた物語がすごく多いんです。国民的なマンガにも、『孤児であるなど、ひとりぼっちの環境で育った主人公が、実は親が偉大だったと知り、力やよりどころを得る』というストーリーがめちゃくちゃたくさんある。そのつながりは分かりやすいし、共感を得られやすいんやろうけど、他にないんか? と思ってしまう」

自身について、「血のつながりがないからこそ、自由でいられた面もある」と話すふくださん。だからこそ、血縁にとらわれるあまり、窮屈さを感じている人が多いのではないかと感じるのだそうだ。
「血がつながっているがゆえに、『親はあんなに優秀なのに、なぜ自分はできないんだろう』とか『自分から生まれたのに、なんでこの子はこんなにちがうのだろう』と思ってしまうこともあると思うんです。私は血のつながりという縛りがなかったから、なりたいものになれるし、どんな可能性もあるんだと思えた」
家族の中の“母”を描くこともまた、ふくださんにとって重要なテーマになった。専門学校の卒業制作「グッバイ・マーザー」では、家を出ていった母の面影を追い求める17歳の主人公を描いた。当時のことを、「“母”を描かずには前に進めなかった」と振り返る。
「小学生の頃でした。兄が難しい時期で、母が数日間、家を出たことがあったんです。18歳から23歳ぐらいの頃は、“母とは何か”をとことん考えた時期でした。私を産んだ人のことも考えていましたし、母親という“枠”に押し込められて、しんどい思いをしている人がたくさんいるのではないかという思いが、常に自分の中にありました。それはフェミニズムの一端であったと、最近になって気付きました。
自分を産んだ人については、20歳になったら調べられると両親から聞いていて、調べる気満々でしたが、母というものを考え、作品として描いたことで満足できたところがあった。1年ほど前に『事情があって自分では育てられず、家族の勧めで手放した』ということだけを、養子縁組あっせん団体である家庭養護促進協会の岩崎美枝子さんから聞いて、それ以上は調べていません。
私にとって、母とは何かを考えることは、同時に自分について考えることだった。自分の人生や気持ちについて飽きるほど考えられたから、27才のときに『自分のことはもう大丈夫かも』と。だから、こどもを育てたいと思えたんだと思います」
いま、あなたに育ててほしいこどもがいっぱいいる
「おいしい家族」の公開を機に、特別養子縁組の当事者であることを公表したふくださん。「自分自身が、世の“一般的”な家族とは違う環境で育った」ことが、作品のテーマを語るうえで、一番わかりやすく、説得力があると考えたからだった。
ただ、この1、2年で「自分の存在が特別養子縁組の周知につながればいい」という思いをはっきり抱くようになったという。
「特別養子縁組制度ができて30年ほど経ち、大人になった養子の当事者が発信しやすい時代になった。そして自分が母になり、こどもを持つ友人が増え、不妊治療をしている友人も多くいる。その環境の変化は大きいかもしれないです。
私の母が養子を迎えることを選んだように、この制度を知らない人が『こどもを育てるのに、こんな選択肢があるんだ』と知ってくれたらいいなと思うようになったんです」

「不妊治療をしている人がみんな養子をとったらいいなんて乱暴なことを言うつもりは、まったくないです。でも、しんどい不妊治療を続ける中で、『自分で産む』ことだけに絞らなくてもいいんじゃないかとも思うんです。“養子は親のためのものじゃない”なんて言うけど、別に“親のため”でもいいと思っています。
妊娠して産みたい気持ちはすごく分かる。けど、『いま、あなたに育ててほしいこどもはいっぱいおるよ』とも思うんですよね。もちろん不妊治療している人だけじゃなく、こどもが欲しいすべての人の選択肢に『産むか、養子を迎えるか』というのが当たり前になればいいなと思います。“養子大国”と言われているアメリカのように」
当事者であると公表したことで、当事者同士のつながりも生まれた。同じ養子として育っても、養親や制度に対して様々な考えがあると知り、自分は自分の考えを伝えていこうと気持ちを新たにしたという。
「私は養子であることを当たり前に知らされてきたから、理解したときも『そうなんや』と思っただけやった。もし養子として引き取ってもらえなかったら、生活に余裕がなくて、映画の道を志すこともなかったかもしれない。映画監督を目指すことすらなかったと思うし、産んでくれた人にも、手放す勇気を持ってくれてほんまにありがとう、と思って生きてきました。
でも、大人になってから真実告知をされた人や、養子であることをネガティブに伝えられてきた人は、養親に対してマイナスな感情を持っていることもある。
私は、真実告知はとにかく早いうちに、絵本の読み聞かせのようにやることが大事やと思うし、同時に『私たちはこういう家族』『あなたのことがものすごく好きだよ』とこどもに伝え続けることが、大切なんやと思います」
もっとゆるく、ただただ可愛がれたらそれでいい
SNSを通じて、養親となった人とつながることも増えているというふくださん。「みんな、子育てにめちゃくちゃ真面目に向き合っている」ことが、最近気になるという。
「真実告知のタイミングや、やり方にも重い責任を感じていて、思い悩んでいる。未知のことだらけだし、気持ちはすごく分かる。ただ、そんな様子を見ると、『もっとゆるく行っても大丈夫』と思うときもあります。子育てに関しては私も初心者なので、あんまり偉そうなことは言えませんが、養子当事者としては、養親になりたい人がたくさんいる中で、縁があってあなたのところに来た子やねんから、ただただ可愛がってください、って。
血のつながりがあろうがなかろうが、荒れる子は荒れる。どう育ったとしても、血のつながりがあるかないかは関係ない。とにかくその子を肯定すること。私の両親がやってくれたように、こどもがやりたいと言ったことに対して『ええやん』と言えるような、おおらかな姿勢が大切だと思います」
人それぞれに違う悩みや苦労を知るようになったいま、養親や養子であることを話せる人がいる大切さにも、気づかされるという。
「振り返ると、母は20年くらいずっと、“養親のサークル”みたいなところに行っていたんです。深い悩みを抱えていた人も多くて、近所の人や周りにはなかなか話せないことも、養親同士、共通認識があるから話しやすかったんだと思う。安心できる場が救いやったんやなと、いまになってすごく思います。こどもに対しても『最近どう?』と定期的に聞いてくれるカウンセラーのような第三者がいたら、両親には言えないけど不安に思ってる子もたくさんいるだろうから、絶対にいいと思います」

手放すことがどれだけ大きな愛かを、伝えていきたい
特別養子縁組制度が、いろんな背景を持つ人たちの選択肢となってほしいという。
「自分事として話すのなら、シングルで子育てをしている人でも養親になるのを認めてほしい。私も『産むか、養子を迎えるか』を考えました。でも、シングルなので制度上、できないんですよね。
もちろん、一定の条件は設けるべきです。でも、両親がそろっていることにちょっと固執しすぎじゃないかと思ってしまう。さらには、男と女である夫婦じゃないといけないというのは、本当に狭き門だと思う。そもそも婚姻制度が古いし、変わるのが遅すぎる。制度が変わることで救われる親が、こどもがどれだけいるか。常々思ってます」

選択肢を広げる、という点で考え続けているのは「手放す側」の視点だ。
「自分を産んでくれた人に対しては、元気でおってほしいし、産んでくれてありがとうと心から思います。ニュースで、公園のトイレで赤ちゃんを産んで捨ててしまった女性や、虐待してこどもを殺してしまった人たちのことを見ると、誰かにこどもを託すと選択することも、どれだけ愛であるか、と思うんです。産んだ人が、自分で育てない選択肢があると知っていること、それを選べること、育ててくれる人が待っていることが、社会にとってどれだけ大事かと。
産む側にも厳しい目があるんだと思います。でも『あなたが産んだからといって、あなたが育てなくてもいいんだよ』という声が届いてほしい。病院でも『辛くなったら、手放していいからね』と言い続ける人がいてほしいと思っています。
人は、ほかに何も選択肢がないと思うとき、最悪な状況に追い込まれていってしまう。『別の道があるんだよ』と知ってもらうために、私が当事者として発信できることをしていきたいと思います」

映画監督、小説家
1991年生まれ、大阪府茨木市出身。
日本映画学校(現・日本映画大学)での卒業制作「グッバイ・マーザー」(監督・脚本)がゆうばりファンタスティック映画祭、下北沢映画祭などに入選。
2016年、小説『えん』が「すばる文学賞」佳作を受賞し、小説家デビュー。
2019年、短編映画「父の結婚」を自ら長編化した「おいしい家族」を監督し、商業長編映画デビュー。国内外の映画祭で上映され、第29回日本映画批評家大賞新人監督賞、おおさかシネマフェスティバル2020新人監督賞を受賞。小説版『おいしい家族』も執筆し、単行本が発売。
2020年、自身の小説『えん』と『ブルーハーツを聴いた夜、君とキスしてさようなら』の2本を基にした映画「君が世界のはじまり」を監督。
2021年、映画「ずっと独身でいるつもり?」を監督。
- すべて
- 養親当事者の想い
- こどもの想い
- 専門家の解説
- 周囲の想い
- 不妊治療