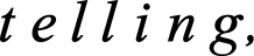体験談を読む
“血縁”がないからこそ、
一緒に過ごす時間を大切にしたい。
池田さん一家

2019年に特別養子縁組で長男を迎えた、会社経営者の池田紀行さんと、不妊ピア(当事者)・カウンセラーの麻里奈さん夫妻。迎え入れる決断までの不安や葛藤、初対面での思い出から、いま息子と育む時間について、話を聞きました。
変わらなかった「子を育てたい」という思い
――お二人は特別養子縁組で2019年に長男を迎え入れました。この選択肢について、考え始めたのはいつごろでしたか。
麻里奈:
制度を調べて知ったのは35歳くらいのときです。30歳から不妊治療をはじめて、この先どうなるだろうと不安があったときに「養子は考えていないの?」と言われたことがあって、「そんな選択肢が日本にもあるんだ」と知りました。
30代後半になれば妊娠率が下がっていくのは分かっていたので、養子縁組を考える人たちが集まるシンポジウムに夫を誘って行ったこともありました。40歳までは不妊治療を続けてほしいと夫に言われていましたが、その先にこんな選択肢も考えられたらいいかな、と。でも、特別養子縁組をしたい、と決めて動くまでには夫婦でいろんな葛藤がありました。
紀行:
当時は、妻から制度のことを聞いても、全く「自分事」化できなかったんですよね。
遠い世界の誰かがするもの、という認識しかなかった。結婚してから流産も経験しましたが、妊娠はしていたので、「自分たちが頑張れば授かれるんだ」という思いがありました。

――そこから、どう考えが変わっていきましたか。
紀行:
二人にとって大きな出来事が、30代後半で死産を経験したことでした。妊娠7カ月での死産だったので、妻の身体的なダメージも大きく、二人の心が折れてしまった。
それまで、治療優先で「こどもができたら、いつかやろうね」と言っていたことがどんどん積みあがっていく生活を過ごしていたんですが、いつ実現するかもわからない夢だけを追い求めるのはやめて、「もう先延ばしはやめよう」と、夫婦で“いつか撲滅運動”を始めました。
長年続けてきた不妊治療を“お休み”し、妻は不妊ピア・カウンセラーの活動を始めました。二人でキャンプを始めたり、海が近い鎌倉に移住したりして、僕はやりたかった自転車やDIY(日曜大工)を始めた。それぞれが夢をかなえていく期間を3、4年過ごしました。
麻里奈:
私は、30代後半に、長い時間をかけて「こどもがいない」ことを受け入れていく準備をしていた感覚でした。不妊という、どうにもならないことを受け入れる、これが私の人生なんだと受け止める作業に数年かかりました。
死産後に、治療に懸けることはもうやめましたが、こどもとの関わりはほしかった。そこで、ボランティア活動として、乳児院のこどもにミルクをあげたり、児童養護施設で育ったこどもたちの、施設を出たあとのアフターケアに携わったりし始めました。特別養子縁組制度を通じて、全国には家庭で育つことができない約4万5000人のこどもたちがいると知って、彼らはどこでどう過ごしているのか、どんな困難があるのか、自分で実際に知りたいと思ったんです。
その関わりの中で、気づいたのが「私は親になりたい」という気持ちでした。こどもを支援する活動はこれからもできるけれど、特別養子縁組では民間のあっせん団体によっては年齢のリミットもあったりする。夫に自分の気持ちを伝えていくのにもリミットがあるなと思いました。

紀行:
妻がそんな思いをあたためていた中、僕は「夫婦二人で歩んでいけばいいや」と思っていました。鎌倉の家もこどもがいない前提で1LDKにしましたし、妻がボランティア活動している様子を「頑張っているな」と見ていた。妻は自分なりの領域で使命を全うしているんだなと思っていたので、そこから僕自身が養子を考えることには全く結びついていませんでした。
変わったきっかけは、妻が子宮疾患で子宮全摘出を決めたときです。1カ月のうち10日間は寝込むほどに症状が酷くなり、このままでは二人での穏やかな暮らしも難しくなると話し合いました。そして、こどもを産める可能性がゼロになるけど、手術しよう、という決断をしました。
その手術後、病室で手紙を渡されました。そこには、「自分で産むことはできなくなったけれど、育てたいという気持ちはなくなっていない。特別養子縁組を考えてほしい」と書かれてあった。考えが大きく変わりました。

ふとした瞬間に入った「父親スイッチ」
――紀行さんの、どんな思いに響いたのでしょうか。
紀行:
僕は、34歳でいまの会社を作ってずっと仕事を頑張ってきました。事業もある程度軌道に乗り、趣味に没頭できるような時間もあった。でも妻は、結婚して十数年もの間、自分の努力ではどうしようもないものと戦ってきていたんです。夫婦ともに、実現したいことに向けて計画を立てて達成してきたタイプだからこそ、努力してもどうにもならないことはものすごくきついことだっただろうなと。
手紙には、「あなたが仕事で成功する姿を見ているのはとてもうれしいけれど、あなたが自分の夢をかなえていくように、私もこどもを育てるという夢をかなえたい」という気持ちがつづられていました。僕が自己実現をしてきた中で、妻は何の夢もかなえていなかったんだと思い知らされ、これからは彼女がかなえる番だと思ったんです。
妻には、「付き合うよ」と伝えました。ぜひやろうとか、ぜひ迎えよう、という思いではなかったけれど、大切な人がそこまで強く思っていることを、「それは知らん」というのなら夫婦とはいえない。妻の思いに付き合い、迎え入れるかどうかを決めるために動き始めました。
麻里奈:
「付き合うよ」という言葉は、一般的には人任せのように聞こえるかもしれませんが、私にとっては「すごく“こっち側”に来たんだ」という感じがしました。それまで5年ちょっとの間、養子に関してはのらりくらりの、つかみどころのない感じの反応だったけれど、「付き合うよ」と言ってくれたのは夫らしい無理のない自然体の変化で、私はすごくうれしかったんです。「それってどういうこと? 退院したら児童相談所に電話していいということ?」とすぐに確認したくらいでした。

――迎え入れる決断へ、どのような行動をしていったのでしょうか。
紀行:
決めるためには十分な検討が必要です。どんな選択肢があるのか、どれくらい時間やお金がかかるのか、養親になる方法は何かといったことを、数カ月かけて調べていきました。
でも、「迎え入れたい」という気持ちが芽生えたのは、思いがけない瞬間でした。
検討の一環として、民間のあっせん団体が行っている一泊二日の説明会兼研修会に参加したのですが、社会的養護について学ぶ座学とともに、沐浴(もくよく)と離乳食を作る研修があったんです。その沐浴で、実際の赤ちゃんと同じくらいの3000gの重さの人形を両手で支えながらぬるま湯に入れたとき、びっくりするくらい人形がかわいいと思えたんです。父親スイッチがいきなり入った感覚になり、説明会が終わってから、すぐに申し込みのメールをしました。
そこから3カ月間は、申し込みをした民間団体での、養親として知識を得るための研修を受けたり、僕らの経済状況や生い立ち、家族構成、居住環境の資料を提出したり、家庭訪問を受けたりと慌ただしく過ぎていきました。
喜びだけじゃない感情を、一緒に抱えていく
――赤ちゃんを迎え入れるまで、そして迎え入れてから、気持ちの変化はありましたか。
紀行:
そもそも特別養子縁組については、「自分には無理だ」という後ろ向きの感情が強かったです。
僕は元々、他人や環境のせいにすることが嫌な性格なのですが、それでももし、迎え入れたこどもが将来何か問題を起こしたり抱えたりしたときに、「血がつながっていない」ことを理由にしてしまうのではないか、というとてつもない怖さがありました。
でも、息子が3歳になったこれまでの日々で、「この子と血がつながっていない」と考えたことは、一度もありません。普通に生活をしていて、養子だとか、血のつながりがあるとかないとか自体を考えたことがない。それは、息子が可愛くてだんだんとなくなっていった、というのではなく、息子がうちに来た瞬間に「なくなっていた」んです。
――麻里奈さんにも、同じ不安はあったのでしょうか。
麻里奈:
それはもちろんありました。周りに血がつながっている親子関係しか見たことがないので、どうなるか分からなかった。
ただ、児童養護施設のアフターケアのボランティア活動を通じて、一緒にいる時間で家族になれるんじゃないかという思いもありました。血がつながっている家族がいても、頼れる存在ではないというこどもたちとたくさん出会い、家族の形に“普通”はないんだと知っていったからです。
不安の中で、血のつながりだけで語れることはないんだと、繰り返し自分に言い聞かせていたのかもしれません。
――赤ちゃんと対面したときは、どんな思いでしたか。
麻里奈:
病室で初めて抱いたときは、「つながれた命を受け取った」という気持ちが大きかったです。当時の写真の顔はすごくかたい表情で、「ついに来てしまった。もう戻れないからしっかりしなきゃ」と緊張感でいっぱいだったんだと思います。
紀行:
普通は、妊娠して体が少しずつ変化していって、準備を重ねて出産のときを迎えます。でも、僕らは数日前に電話をもらって迎え入れることを決めているわけです。
突然、こどもと病室で対面するという出来事が、点として打ち込まれるような感覚です。僕も、「責任のある父親になってしまった」と理性で考えていた感じで、緊張と責任と喜びと、いろんな感情が入り混じっていましたね。
麻里奈:
喜びだけがあるのではなくて、こんなに小さな生まれたての子が、産みの親と暮らせないという事実も突きつけられます。お母さんはひとりで退院していくと聞いていて、こんなに元気に産んでも、育てられない事情があるんだなと考えると苦しかった。辛い出来事も一緒に抱える、一緒に背負っていく感じがしましたね。

こどもの目を見つめ、言葉をかける時間を大切に
――日本の特別養子縁組制度について、課題を感じたことはありましたか。
紀行:
特別養子縁組を検討する際に、役所にも足を運び情報収集をしましたが、公的な研修制度が、まだ養親候補の生活実態とは合っていない課題があると思いました。例えば30代~40代は仕事も忙しい時期でもある。もっと柔軟に日程を組めるようにしなければ、現状は改善していかないのではと思います。
麻里奈:
民間のあっせん団体は、その点で細やかなフォローがありますが、コストはかかります。不妊治療を経て特別養子縁組を考える方は、治療費にたくさんのお金をかけてきた方も多い。民間団体への助成金などの仕組みも、より充実していくといいなと思っています。
――養親支援、子育てのサポートという点での課題感はありますか。
麻里奈:
私たちが利用した民間のあっせん団体では、アフターサポートが充実しており、幸運にも課題を感じたことはほとんどありませんでした。
例えば、審判確定までの期間に家庭訪問が2回あり、毎月提出する育児日記に何か変化があればすぐに電話がかかってきます。養親同士やあっせん団体の方とつながるグループLINEもあって、子育ての相談もできる。養親には“産院”がないので、母親同士がつながる機会がなかなかありません。だからこそ、養親が孤立しないようにするためにもアフターサポートの手厚さは大事だなと思います。
息子を迎えてすぐのときには、「真実告知」の研修にも参加しました。今のグループLINEはみんな、こどもが2~3歳の養親たちなので、こどもに出自をどう伝えるかが大きなテーマです。
うちでは、赤ちゃんのころから「うちに来てくれてありがとう」「本当に幸せになったよ」と毎日のように言っています。いまは、産みのお母さんの名前も伝えて、「産んでくれたお母さんとお父さんがいるんだよ」と話しています。答えのないことなので、「こんなとき、どうしてる?」と相談できるコミュニティがあることは、とても心強いですね。

――養子を迎え入れることに対して、家族や友人など周りの反応はいかがでしたか。
紀行:
不妊治療をしているときから、周りにもオープンにしてきたので、「養子を検討しようと思う」「ついに待機家族になった」という話も、仕事仲間や友人たちに包み隠さず言っていました。
ただ、両親には少し遠慮がありました。流産や死産でつらい思いをしてきたのをずっと見てきているので「何もそこまで苦労しなくても」と思っているんじゃないかな、と。養子には、人の子を預かって苦労する、という認識があるだろうなと思っていたんです。
でも、両親は血がつながっていなくても、いま息子が可愛くてデレデレです。
麻里奈:
世の中的には、「養子は大変」と言われることはまだまだあると思います。
でも、ママ友の多くは若くて多様性を受け入れている世代。ママ友同士では「どこで産んだの?」とか「似ているね」という話題が必ず出てくるので、その都度「実は特別養子縁組なんだ」と話しています。
地域の支援センターで仲良くなった友人や、保育園、今入っている自主保育のサークルなどいろんな新しい場がありますが、誰もがすんなりと「それはよかったね」「聞いてあたたかい気持ちになったよ」と言ってくれる。周りの環境にはすごく救われています。
息子が3カ月のとき、親戚が集まる場に連れて行ったときも、「抱っこさせて」と息子をみんなが囲んでくれた。赤ちゃんのパワーはすごいな、と改めて思いましたね。
――息子さんを育てている中で、大事にしていることは何ですか。
紀行:
息子は、遺伝的に受け継いでいることが一切ありません。だからこそ、一緒にいる時間で、どれだけ影響を与えてあげられるかがすべて。できるだけ多くの時間を過ごす中で、いつも目を合わせて“見てあげる”ことを意識しています。
どんなに小さくても、言葉で説明することも大切にしています。どうしても言うことを聞かないときでも、感情的に怒るのではなくて、何をやったらいけないのかを言葉にして説明する。それでもわからないときは、怒らず、叱る。赤ちゃん言葉は使わずに、一人の人間として接するようにしています。
もう一つは、いっぱい笑うことかな。一緒に笑うことを心がけながら、喜怒哀楽のある子になってほしいなと思っています。

まずは夫婦それぞれが考えて、会話することから
――これから養子を迎えようと考えている方へ、伝えたいことはありますか。
紀行:
大事なのは、夫婦でとにかくたくさん会話をすることだと思います。
妻とはお互いに言いたいことを言い合える夫婦だと思っていましたが、養子はすごくデリケートなテーマ。「相手は嫌がるんじゃないか」「答えにくいんじゃないか」と最後まで遠慮がある領域だと思います。
でも、血のつながらないこどもを迎え入れる準備をしていくためには、夫婦が同じくらい深く考えて、思考が成熟している状況にいなくてはいけない。努力して、意識的に会話をしなければすり合わせられないことだと思っています。「一緒に暮らしているから、相手のことはよくわかっている」と思いがちですが、実は全然理解できていなかったりするんですよね。しかも、養子は難しいテーマなので、普段から話しにくいことを話し合える関係じゃないと、会話が深まっていきません。
目的や課題に向き合うために、妻は、僕とちゃんと話したいときは「〇〇についてご飯を食べながら話したい」などとアポを取るんです。夫婦間でどんなことも言い合える土台作りも欠かせないと思います。
――麻里奈さんは、不妊ピア・カウンセラーの活動もされています。
麻里奈:
37歳から活動し10年になります。実際に養子を迎えてからは「養子を迎えたいので当事者の話を聞きたい」という相談が多いです。そのなかでお聞きしているのは、「どうして養子縁組を考えているのですか」という問いです。それは自分への問いでもあったのですが、それがいま心の支えになっている。こどもが欲しいから不妊治療を続けているという気持ちはよくわかります。ただ、みんなと一緒になりたい、「普通」になりたいからこどもを迎える、ということではないということは、早いうちから考えてほしいと思っています。
紀行:
僕は、妻から特別養子縁組の話を持ち掛けられても、いつものらりくらりとごまかしていました。養子とは、社会的養護のために“自己犠牲的な愛”で育てるものだと思っていて、自分には絶対無理だと避けていた。
でもだからこそ、そんな等身大の自分を包み隠さず発信することに意味があるかなと思っています。僕みたいに意識が低かったような人間でも、よく考えて夫婦で話し合った末に、養親として幸せに暮らしている。息子から「パパ、パパ」と言われるようになって、ようやく「自分はパパなんだ」と自覚し始めています。僕が父親になっていったというよりは、息子が僕を父親にしていっているんです。
最初から覚悟や決意のある人なんていませんから、研修会や勉強会に行ってみて、検討してみればいい。情報を調べるだけ調べてから、受けるか受けないかを決めればいいんです。僕だって、たまたま沐浴で父親スイッチが入ったわけで、何がどう変わるかは分かりません。まずはそんな心構えからでも大丈夫だということを、多くの男性に知ってもらいたいですね。
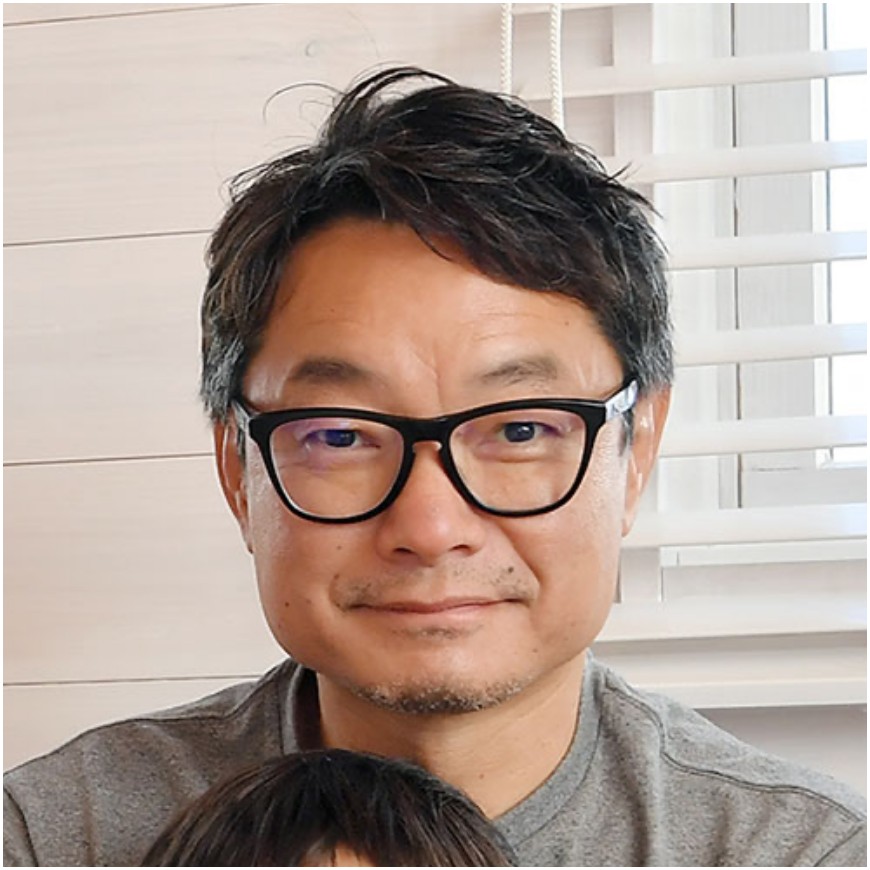

- すべて
- 養親当事者の想い
- こどもの想い
- 専門家の解説
- 周囲の想い
- 不妊治療